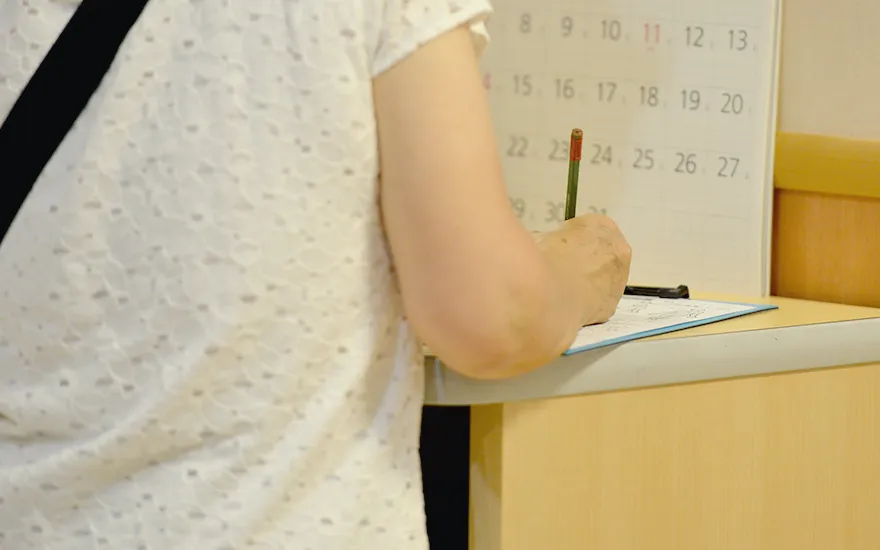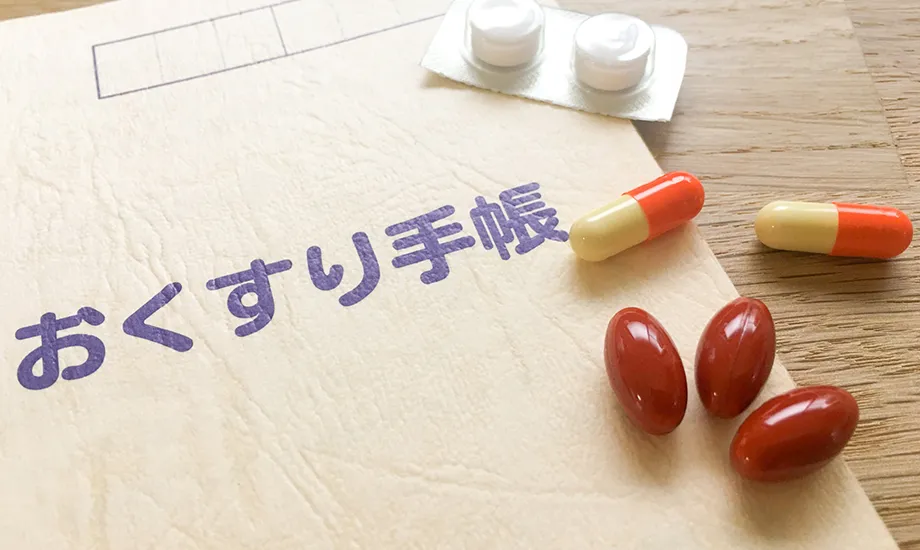簡易検査について
簡易検査について

小型の携帯装置を自宅で一晩装着します。下図のように鼻(呼吸)と指(血液中酸素濃度と脈拍)にセンサーを装着します。装置が空いていれば、当日貸出(翌朝返却)ができます。
簡易検査の概要

装置自体は携帯電話程度の大きさですが、センサーなどを含めてハンドバッグ位の袋に入っています。
簡易検査装置(LS-120)図解
少し小型のLS-120を使用された方には、多少異なる点があります
本体装置


ベルトは強く締めすぎないでください。
SpO2センサの装着
センサは左手人差し指に取り付けて、ケーブルを手の甲側から発光部を爪側にして、サージカルテープで固定して下さい。


- センサを取り付けたらLS-100をスタートし、ハートマークが点滅していることを確認してください。点滅していない場合、点滅するように再度センサを取り付けなおしてください。
- テープは強く締め過ぎないでください。
- センサが外れた場合、再度取り付けなおしてください。
カニューラの装着
カニューラを鼻に装着し、両耳に掛けてから、ストッパで調節し、サージカルテープで固定して下さい。

- カニューラはおれないように注意してください。
- カニューラの鼻腔管は自分の方に向くように装着し、鼻孔内に入れて下さい。
- カニューラが外れた場合、再度取り付けないでください。
部品が足りない気がするのですが?

ポーチにはLS-100、TG-30(SpO2センサ)、カニューラ、サージカルテープ、説明シート、リストベルトを入れます。
器具の返却を延長できませんか?
翌日検査の予約をしている方のために、申し訳ありませんが、必ず返却してください。
ボタン操作の誤りなどで、記録ができていなかった場合はどうするのですか?
回収した器具を解析して、やむを得ない理由(ボタン操作の誤りなどを含みます)でデーターが得られなかった場合は、2回目の再検査は無償で実施します。
忙しいので、簡易検査は省略して入院検査をしたいのですが?
健康保険の規定で、簡易検査を先行することが原則となっているのです。まず、簡易検査をお願いします。
一夜だけの簡易検査で判断できるのですか?
夜の無呼吸の程度に大きな差はありませんので、過度の飲酒などを毎特別な理由がない限り、一夜の検査で診断は可能です。
鼻カニューラは、清潔ですか?
使い捨ての新しいものを使用しています。
腕と指への図が小さくて分かりにくいのですが

左利きなので、腕と指は右側でもよいでしょうか
全く問題ありません。
鼻カニューラは鼻の奥まで入れた方がよいのでしょうか?
鼻カニューラで呼吸による微弱な鼻腔圧の変化を測定するので、痛くない範囲でなるべく奥まで挿入してください。

睡眠中は口を開けてしまうのですが、大丈夫でしょうか?
口を開けると精度は低下しますが、診断にはほぼ差し支えありませんので、ご心配なく。
電池や記録の容量は十分ありますか?
24時間は検査ができる容量があります。
スタートボタンを押しても動作しないのですが?
スタートボタンは、2〜3秒押し続けないと動作を解しません。

「装置が正常に動作しているか?」の確認はどうしたらよいのでしょうか?
- 画面の左上に「REC」が表示されれば、電源が入った状態です。
- 画面中央の%Spo2の下に90:から99:の間の数字(血液酸素の量)が表示されていれば、指センサーは正常作動中です(右隣のBPMの下にも50から120の間の数字(脈拍)が表示されます)。
画面下中央右寄りの「フロー」の文字の上の縦線が呼吸に応じて増減すれば、鼻センサーも正常作動中です。

ストップボタンを押しても、動作が終了しないのですが?
終了時は電源ボタンを画面が消えるまで押し続けてください。動作が終了しないので再度押す時は3秒以上あけてから押して下さい。
夜間にトイレに行くときは、センサーを外してよいでしょうか?
電極のつけ外しは検査の中断と判断されるため、記録失敗の原因になることが多いので、なるべく装着したままでトイレへ行ってください。
この結果で治療に入れるのですか?
簡易検査は睡眠の程度を評価することができないのと、精度が十分ではないので、CPAP治療を行う場合は入院検査が原則的には必要です。
簡易検査だけで、CPAP治療を開始した人の話を聞いたのですが?
非常に重症の方は緊急措置として、簡易検査のみで治療を先行させる場合があります。
しかし、睡眠時無呼吸症候群は長期にわたって治療が必要なので、入院の上で正確な診断のための検査(ポリソノグラフ)を行うべきです。
簡易検査の装置を破損したら修理にいくらぐらいかかりますか?
装置は高価(数十万円)なので、大切に扱って下さい。
装置が気になって眠れません
検査を受ける方の条件は皆同じですから、緊張をなるべく解いて目を閉じていれば、多くの方は検査に必要な時間は睡眠できます。
検査には、最低どのくらいの睡眠時間が必要ですか
眠りには周期があるので、正確な検査には3時間以上の睡眠が欲しいものです。
何度も目が覚めましたが大丈夫でしょうか
簡易検査は睡眠をしているかの判断がしにくいので、検査精度は低下しますが、ほとんどの方で解析そのものは可能です。
いつも睡眠薬を飲んでいるのですが…
睡眠薬は結果に影響がありますが、いつもの状態を記録した方が良いので、いつも通りに飲んでください。
お酒はだめですか
飲酒は結果に影響がありますが、いつもの状態を記録した方がよいので、普段より少な目ならば構いません。飲み過ぎると結果がひどく悪くなるので、注意してください。
結果を自分で見られませんか?
元データを差し上げることはできませんが、詳細な解析レポートをお渡しします。
もし、結果が軽症だったときは、来月もう一度検査して貰いたいのですが
健康保険上の製薬があるので、ご希望があっても次の検査には3か月程度はあける必要があります。
動作不良時のエラー表示
参考
| PRO6E | 酸素センサーの外れ、ないし不適切な装着 |
|---|---|
| M6:17V | 電池残量不足 |
| ERR.002 | 上記以外のエラー |
簡易検査の記録例
一晩中無呼吸を繰り返す重症の方もいますが、さほど重症でない方では無呼吸を繰り返す時間帯と普通の呼吸を繰り返す時間帯が交互にあります。
同一人物の無呼吸頻発反復時(左図)と普通の呼吸(右図)の記録を比較してみましょう。これは簡易検査の記録ですが、かなり正確に分かるものです。
一番上の紫色の帯が呼吸の様子です。右の図では幅が一定なのに、左図では断続した帯となっており、この帯の数十秒間途切れた部分がすべて無呼吸です。途切れていない部分をよくみると右図も左図も一本の帯ではなく、小さな波(ぎざぎざ)から構成されています。これが一つ一つの呼吸なので、左図を見直すと、数回大きな呼吸をした後に数十秒の無呼吸が起きていることが分かります。
普通呼吸の時には、血液の酸素量(青線)は97から全く動きませんが(右図)、無呼吸で呼吸が繰り返し停止すると酸素も繰り返し低下しています(左図)。ときには、橙色の安全境界線を下回って、一時的に酸欠(呼吸不全)状態となっています。
酸素の低下時には、脈拍(緑線)が上がっており、無呼吸は心臓にも強い影響があることがわかります。
無呼吸時には、普通呼吸では目立たなかったいびき(茶色線)が強くなり、呼吸が止まるごとにいびきも消えています。

費用についてのご質問がある方は、医事課入院会計係を呼び出して下さい。
-


 内科(初診)
内科(初診) -


 総合内科
総合内科 -


 呼吸器内科
呼吸器内科 -


 循環器内科
循環器内科 -


 肝胆膵・消化器病センター
肝胆膵・消化器病センター -


 内視鏡内科
内視鏡内科 -


 内分泌・糖尿病内科
内分泌・糖尿病内科 -


 腎臓病センター(腎臓内科)
腎臓病センター(腎臓内科) -


 脳神経内科
脳神経内科 -


 機能的神経疾患センター(機能神経外科)
機能的神経疾患センター(機能神経外科) -


 リウマチ・膠原病・アレルギー科
リウマチ・膠原病・アレルギー科 -


 緩和ケア内科
緩和ケア内科 -


 脊椎センター・脊柱側彎症センター
脊椎センター・脊柱側彎症センター -


 心臓血管外科
心臓血管外科 -


 脳神経外科
脳神経外科 -


 整形外科
整形外科 -


 外科
外科 -


 皮膚科
皮膚科 -


 小児外科
小児外科 -


 小児科
小児科 -


 新生児内科
新生児内科 -


 形成外科・美容外科
形成外科・美容外科 -


 泌尿器科
泌尿器科 -


 眼科
眼科 -


 耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科 -


 産科・婦人科
産科・婦人科 -


 高精密度放射線治療センター
高精密度放射線治療センター -


 放射線診断科
放射線診断科 -


 救急センター(ER)
救急センター(ER) -


 麻酔科
麻酔科 -


 痛みセンター(ペインクリニック)
痛みセンター(ペインクリニック) -


 脳卒中センター
脳卒中センター -


 集中治療科
集中治療科 -


 病理診断科
病理診断科 -


 精神科
精神科 -


 人間ドック・健診センター
人間ドック・健診センター -



 看護部
看護部 -



 診療看護師(NP)
診療看護師(NP) -



 放射線部
放射線部 -



 薬剤部
薬剤部 -



 リハビリテーション室
リハビリテーション室 -



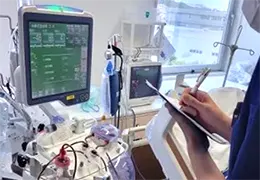 臨床工学科
臨床工学科 -



 臨床試験センター
臨床試験センター -



 医療相談室
医療相談室 -



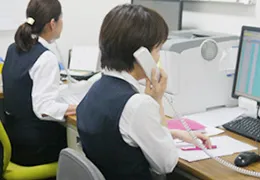 地域医療連携室
地域医療連携室 -



 国際医療支援室
国際医療支援室 -



 院内保育園「かもめ園」
院内保育園「かもめ園」 -



 湘南藤沢徳洲会介護センター
湘南藤沢徳洲会介護センター -



 湘南藤沢訪問看護ステーション
湘南藤沢訪問看護ステーション
-


 内科(初診)
内科(初診) -


 総合内科
総合内科 -


 呼吸器内科
呼吸器内科 -


 循環器内科
循環器内科 -


 肝胆膵・消化器病センター
肝胆膵・消化器病センター -


 内視鏡内科
内視鏡内科 -


 内分泌・糖尿病内科
内分泌・糖尿病内科 -


 腎臓病センター(腎臓内科)
腎臓病センター(腎臓内科) -


 脳神経内科
脳神経内科 -


 機能的神経疾患センター(機能神経外科)
機能的神経疾患センター(機能神経外科) -


 リウマチ・膠原病・アレルギー科
リウマチ・膠原病・アレルギー科 -


 緩和ケア内科
緩和ケア内科 -


 脊椎センター・脊柱側彎症センター
脊椎センター・脊柱側彎症センター -


 心臓血管外科
心臓血管外科 -


 脳神経外科
脳神経外科 -


 整形外科
整形外科 -


 外科
外科 -


 皮膚科
皮膚科 -


 小児外科
小児外科 -


 小児科
小児科 -


 新生児内科
新生児内科 -


 形成外科・美容外科
形成外科・美容外科 -


 泌尿器科
泌尿器科 -


 眼科
眼科 -


 耳鼻咽喉科
耳鼻咽喉科 -


 産科・婦人科
産科・婦人科 -


 高精密度放射線治療センター
高精密度放射線治療センター -


 放射線診断科
放射線診断科 -


 救急センター(ER)
救急センター(ER) -


 麻酔科
麻酔科 -


 痛みセンター(ペインクリニック)
痛みセンター(ペインクリニック) -


 脳卒中センター
脳卒中センター -


 集中治療科
集中治療科 -


 病理診断科
病理診断科 -


 精神科
精神科 -


 人間ドック・健診センター
人間ドック・健診センター -



 看護部
看護部 -



 診療看護師(NP)
診療看護師(NP) -



 放射線部
放射線部 -



 薬剤部
薬剤部 -



 リハビリテーション室
リハビリテーション室 -



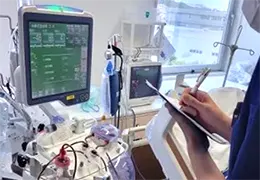 臨床工学科
臨床工学科 -



 臨床試験センター
臨床試験センター -



 医療相談室
医療相談室 -



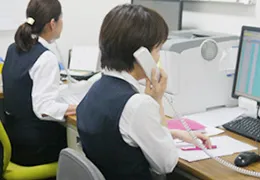 地域医療連携室
地域医療連携室 -



 国際医療支援室
国際医療支援室 -



 院内保育園「かもめ園」
院内保育園「かもめ園」 -



 湘南藤沢徳洲会介護センター
湘南藤沢徳洲会介護センター -



 湘南藤沢訪問看護ステーション
湘南藤沢訪問看護ステーション